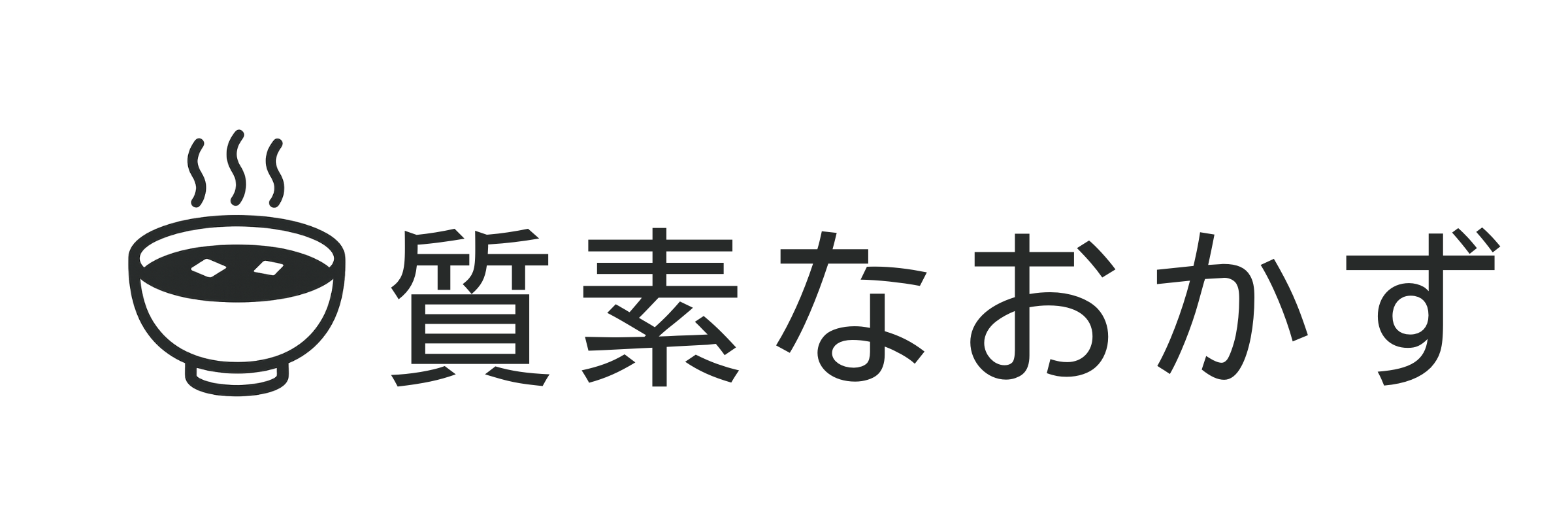本サイトは、「節約・時短・ヘルシーの3つが同時に成立している食生活を目指したレシピサイト」になります。
背景
食べることは生きることであり、食べることは娯楽でもあります。
でもだからといって、食べることにコストがかかりすぎていたり、調理に手間と時間がかかりすぎていたり、おいしものを食べていても体調が乱れたりする。
それでは本当に豊かな暮らしになっているのかは疑問が残ります。
「節約」「時短」「ヘルシー」
これらは同時に成り立っていることが、僕は豊かな食生活だと思っています。
この食生活のことを、”質素な食生活” と呼びたいと思います。
・節約だけを追求したレシピはあります
・家事の時短だけを追求したレシピはあります
・健康的で栄養バランスを追求したレシピはあります
ですが、これらが融合しているレシピ(というよりも思想?)は見つかりません。
「ないなら自分で作ってやろう!」
そう思って生まれたのが、本サイト【質素なごはん】になります。
そして、レシピだけではそんな食生活は実現できないため、以下にコツをまとめておきたいと思います。
栄養バランスの基本的な考え方
節約と時短はわかりやすいですが、ヘルシーには正解がありません。
そこで本サイトで展開する質素な食生活は、以下の栄養バランスを重視した考え方になっています。
① 炭水化物
→主食はお米です。小麦粉主食でヘルシーな食事は相当難しいです。
② たんぱく質
→手軽に調理できる「卵」と「納豆」を毎日の献立に組み込み、お肉やお魚は作り置きしておきます。
③ ビタミン
→細かいビタミンのことは考えません。考えることは大量のビタミンを流し込むことであり、野菜の副菜常備と味噌汁の具材に野菜やキノコを多様します。
④ 食物繊維
→腸内環境を整える上で重要になる食物繊維は、基本的に味噌汁で取ります。こんにゃくや海藻といった味噌汁と相性のいいものは水溶性食物繊維なのでお通じがよくなります。
→あと、お米に水溶性食物繊維が豊富なもち麦を混ぜて炊くといいです
⑤ 発酵食品
→腸内環境は栄養バランスと同じくらい体調に関係します。発酵食品は腸内を整えるので、味噌や納豆を毎日の食事の中で取ることになります。
前提編
質素な食生活は事前準備が肝になります。
平日質素、休日ちょい贅沢の法則
食べることは楽しいことだからといって、平日は仕事で忙しいです。
そのため、平日は質素なごはんに徹すること。
でもその代わりに、休日にちょっと贅沢な食事を作る。
平日と休日でハイブリッドな食生活を考えることが、まずは質素な食生活の土台になります。
自炊のやる気が出る道具を揃える
気の持ちようだけでは料理は楽しくなりません。
料理を楽しめるだけの環境を整えることが重要になります。
器から調理器具、食卓の環境作りなど、調理そのものよりも、こういった調理が始まる前の環境構築のほうが遥かに重要になるわけです。
【→環境構築のページは準備中】
ローリング作り置き生活が基本
質素なおかずで紹介するレシピは、「お弁当のおかずにも使える作り置きレシピ」を掲載しています。
作り置きすることによって、食材のロスをなくし、家事の負担を下げ、食べる分だけ取り分けることでヘルシーな食生活を実現します。
ですが、週末に何品も作り置きしたら半日潰れてしまします。
そのため、その日食べる分のおかずを一気にまとめて作り、食べる分だけをお皿に盛り付けたら、残りを保存するという「ローリング作り置き生活」を推奨しています。
朝ごはんの脱小麦
手軽に支度ができて人気のトーストですが、自覚がないだけで小麦の摂りすぎは体の気だるさの原因のひとつになっていることがあります。
そのため、朝ごはんにはパンを食べないことが基本になります。
代わりに、ヨーグルトやオートミール、果物といった超軽食を推奨しています。
献立の基本の型を決めておく
詳しくは、「質素な献立理論」のページで紹介していますが、1日3食の基本の型を決めること。
これが質素な食生活で重要になります。
毎日作るものをゼロから考えていたら、料理が大変になってしまって当然です。
平日は献立を固定化することで家事の負担を減らすことで生活を楽しみ、それが結局は、節約やヘルシーな食事にもつながっていきます。
買い物編
料理とは作るだけではなく、むしろ買い物のほうが時間や精神力を使います。
スーパーに行く曜日を固定する
毎日スーパーに行ったり、気分でスーパーに行ったりしていると、その分だけ時間がかかるようになります。
また、スーパーに行くことで「なんでも買えてしまう状況」を作ってることが、お菓子やお酒などの余計なものを買ってしまう最大の原因でもあります。
そのため、「週に2日、水曜日と土曜日だけ」のようにスーパーに行く日を固定します。
節約のためにスーパーをハシゴしない
節約のためだけに買い物する場所を変えるのはやめます。
なぜなら、いろいろなお店に買い物に行くこと自体が疲れやストレスの原因であり、その溜まった疲れやストレスを発散するために別のところで支出が増えているからです。
この間接的な関係性は目に見えにくいからこそ、厄介です。
ラクをできるところでは手を抜くことが、節約生活においても、豊かな生活においても大切です。
玄米を30kg単位でまとめてストック
お米は大量にまとめて買ったほうが単価が下がります。
それに、なくなるたびに買い物に行くのも大変です。
一方で、精米されたお米を買ってしまうと、時間が経てば経つほど味が落ちてしまいます。
ですので、玄米の状態で20kgや30kg大容量のものを購入し、家で保管するようにします。
そして、「家庭用の小型の精米機」を持つことで、お米を炊くたびに精米したほうが毎日おいしいお米を食べられます。
お米にはもち麦を混ぜて炊く
精米したお米には、もち麦を混ぜて炊きます。
もち麦は白米に比べて圧倒的に水溶性食物繊維が多いので、お通じがよくなります。
それに、もち麦は国産のものでも1kg500円程度で買えるので、玄米や白米を買うよりもむしろ安いと思います。
1kgのもち麦を混ぜたら、それは1kgのお米が増えるのと同じ意味なので、白米ともち麦を混ぜることにはメリットしかありません(味が嫌いじゃなければ)
自然素材系のおやつをストック
小麦粉や砂糖、油をたくさん使ったお菓子はおいしいですが、中毒化します。
そういったお菓子はコストも安いことが厄介で、安いからこそ依存してしまっているわけです。
一方で、果物やナッツといった自然素材のものはコストが高いのですが、栄養が豊富で適度な量であればむしろ食べたほうが体調がよくなります。
なにより、中毒化しません。
そのため、小腹が空いたときにつまめる自然素材のおやつをストックしておきます。
野菜は旬のものを買う
毎日の食事というと、バリエーションを求めてしまいがちです。
ですが、食べ物とは風土や季節によって身体が欲しているものが変わります。
春には春の食べ物が、夏には夏の食べ物が、秋には秋の食べ物が、冬には冬の食べ物があるものです。
そのため、レシピサイトを参考にしつつも、そのとき安い旬の野菜をベースに、同じようなレシピを何度でも作って食べればいいです。
すると、コストが下がるだけでなく、体調もよくなっていきます。
使用頻度の少ない調味料は買わない
自炊しているのにコストが高くなってしまったり、自炊しているのに体重が増えてしまったりするのは、調味料がひとつの原因かもしれません。
調味料は増えれば増えるほどお金がかかり、しかも、砂糖や油がたくさん入っているので “隠れカロリー” を摂取することになります。
味付けというのは、複合された市販品ではなく、自分で調合すること。
すると、コストが下がるだけでなく、ヘルシーなおかずに調整できます。
詳しくは、「質素な調味料理論」のページでもまとめています。
調理編
調理はシンプルにすることで手間が減るだけでなく、節約とヘルシーも同時に成立するようになっていきます。
1品で具材は3種類までにする
たくさんの具材を使えば、料理はおいしくなるというものではありません。
むしろ、食材は混ぜれば混ざるほどに味がぐちゃぐちゃになります。
当然、手間やコストも上がります。
ですので、1品のおかずに使う食材は多くても3種類までにすること。
本サイトで紹介しているレシピも基本的にそうなっています。
味付けのベースは醤油×乾物
味付けは複雑にする必要はありません。
むしろ、複雑な味付けにしようとあれこれ調味料を入れているうちに大味になり、すべて同じような味になってしまいます。
質素なおかずの基本的な味付けは、醤油と乾き物です。
食材に塩こしょうで下味をつけ、醤油やみりん(もしくは砂糖)で甘みを出し、味の奥行きには乾き物(昆布、わかめ、桜えび、切り干し大根、ドンコなど)を使う。
乾き物といって出しを取るわけではなく、そのまま具材として使います。
料理研究家である魚柄仁之助さんの著書『うおつか流台所リストラ術 ひとりひと月9000円 』の理論を取り入れた考え方になります。
葉物野菜はレンジ調理でおひたし
小松菜やほうれん草、キャベツといった葉物野菜の作り置きにはレンジを活用します。
火を使わずに調理できるようになるだけで、料理の手間は大幅にカットすることができます。
しかも、十分すぎるほどにおいしく作れます。
根菜は簡易漬物にする
大根や人参といった根菜についても、レンジを使うことで簡単に下茹ができます。
もしくは、適当なサイズに切ったら生のまま、「塩や白だし、乾き物、酢、味噌」などを揉み込み、あとは冷蔵庫で放置するだけの簡易漬け物も作れます。
これも立派な副菜の1品です。
味噌をお湯を溶くだけのパターンもあり
質素な食生活では、味噌汁を主菜とします。
野菜やキノコ、海藻、豆腐や油揚げなどの大豆だけでなく、お肉やお魚なども放り込んで煮込んでしまえば、栄養満点で食べ応えのある1品になります。
一方で、思いっきり手を抜いて1品にすることもできます。
汁椀に味噌や白だしを入れ、乾燥わかめや小さく切った豆腐などを入れて溶くだけ。
おかずがあって汁物がちょっとほしいときはこれで十分です。
納豆に一手間加えて副菜に進化
納豆も立派な副菜の1品です。
大豆なのでたんぱく質も豊富で、腸内環境を整える発酵食品でもあります。
そのままでもおいしい納豆ですが、刻みネギを入れたり、漬け物を小さく切って混ぜたり、乾き物を加えたりなど、一手間加えるだけでさらに立派な副菜に進化します。
だし巻き卵をレギュラー化する
卵は、安くて、うまくて、たんぱく質もビタミンも豊富で、しかも、生でも、焼いても食べられる最強食材の一角です。
そのため、卵を毎日のおかずの1品として固定します。
おすすめはだし巻き卵で、卵に白だしを少し垂らしたら焼くだけ。
これだけでお弁当のおかずの1つにもなります。
豚→魚→鶏→魚→豚のローテーション
これは明確にする必要はありませんが、主菜となるお肉とお魚は交互だとうれしいです。
お肉は「豚」と「鶏」が基本になるので、豚を食べた次の日は魚(缶詰も含めて)を、その次の日はお肉でも鶏を食べて、その翌日はまた魚…。
といった具合でローテーションするとバランスがよく、食べ飽きないです。
揚げ物はお惣菜に託す
自宅で揚げ物は諦めます。
もちろんやってもいいのですが、少なくとも平日はやらないと決めてしまうといいでしょう。
どうしても揚げ物を食べたいときは割高でもスーパーでお惣菜を買い、ありがたくいただくことにしましょう。
以上